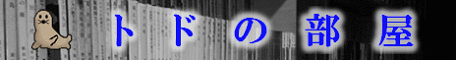三和土(たたき)
施工したのは家の側面の幅1m長さ8m程の土地。その上の壁を直したのですが、土のままでは雨が降った時の跳ね返りが酷く。
セメントで固めるのは嫌だし、かといって「固まる土」は妙に高価だし(1500円/㎡)。と言う訳で三和土に挑戦。
ちゃんとできましたが、これを見て作ろうと考えておられるのなら最初に忠告。大変ですよ!
三和土とは
三和土(たたき)は、「敲き土(たたきつち)」の略で、赤土・砂利などに消石灰とにがりを混ぜて練り、塗って敲き固めた素材。3種類の材料を混ぜ合わせることから「三和土」と書く。 土間の床に使われる。(Wikipediaより)
最近では「ザ!鉄腕!DASH!!」で使われて有名になりましたが、セメントが西洋から伝わる前に日本中で使われていた伝統的な在来工法です。
材料
- 土は、ネットで調べると「京都深草の深草土が良い」などと書かれてますが、それは高級家屋の庭などに使う時などの話。元々在来工法なのですから、そこいらにある土でやってしまいます。我が家の場合、元々の土が花崗岩質ですからそのまま使用します
- 消石灰は農業用の20㎏で500円程の一番安いやつ。
- にがりは探し回ったのですが食用しか見当たらず、これが異常に高価。
調べるとにがりを入れる目的は冬場の凍結防止であり塩化カルシウムでも代用できると書いてありました。そこで目をつけたのが押し入れ用の除湿剤。いろんなタイプが有りますが、使っていると液化するのは塩化カルシウム。その液化したのを家内に提供してもらいました。


必要な道具
- タコ:土を突き固めるために使います。売ってますがバカみたいの高い(2~3万円)。
結局そこいらの端材を使って自作しました。頭部は柱の余り材です。 - フネ:これも外壁を直すときに外した木目トタン板が有ったのでそれをひん曲げて自作。
- 鏝(コテ)類:鍬、手持ちのスコップ、仕上げ用の鏝。あるもので適当に。
作り方
「土と消石灰の配分は土の種類によって変わるので、サンプルを作って決めなさい」とのことでまずは試作。
20㎝角で深さ3㎝ほどの木枠を3個造り、そこに土と消石灰を体積比で3:1,4:1,5:1の比率で混ぜ水を加えて良く練った材料を入れ、突き固めます。
丸一日放置後、硬さを確認して4:1で行くことにしました。
防湿剤はいい加減です。1㎡あたり400ml位でしょうか。
- 最初に水勾配を取って地面を綺麗に均します。この土地の場合
長手方向は、中央部を高くして前後に1m当たり3㎝の傾斜を取りました
また短手方向は家側を高く、境界のブロックに向けた傾斜をつけます - 地面の表面を5㎝ほど削り取ってフネに入れます
- 削り取った地面の境に仕上がりの水勾配の高さに木の棒をセットします
- フネの土に消石灰を加え、土の塊を崩しながら良く混ぜます(からねり)
- この過程で出て来た小石は元の地面に返してタコで突いて埋め込みます
- 塩化カルシウムを混ぜた水を加えて練ります。水気が全体が行き渡り、握ると固まるレベルです。
- 一度に戻すと扱いにくいので、まずは半量を戻してタコで突き固めます。
- さらに残りを戻してタコで突き固める。次第に表面に水気と土と石灰が混ざった細かい粒子が浮き上がってきます
- 予め埋め込んだ木の棒の表面(=水傾斜)に沿って、表面を鏝で仕上げる
コンクリートミキサーでもあれば簡単なのですが、人力でやるとなると土を混ぜるのも大変です。フネの大きさで一度に出来るのは0.3㎡分ほど。全工程を回すと1時間弱。1日3度回してやっと1㎡です。

施工中と未施工の間に水勾配の木の棒が見えると

見た目はほぼセメント仕上げと一緒です。
右の写真の手前側を2017/10に作り、一旦中断。その後2018/04に向こう側をやりました(まだ十分乾燥していない)。
つぎはぎになりましたが仕上げとしては満足です。
ただ、最初にも書いたよう予想以上の力仕事で、これだけの面積なら一人でやる仕事じゃないですね。
昔は5人10人集まって、一気に仕上げたのでしょうね。セメントに駆逐されるのももっともだと思います。
【2020年追記】
施工後3年立ちました。表面は多少荒れましたが、ひび割れも無くいまでもしっかりして居ます。
多少表面にうねっていて雨後に水がハケ無い場所があり、少し苔が付くようになりましたが、これも在来工法。コンクリートだと許せないのでしょうが、三和土ならそれも自然のような気もします。
ちなみに、その後別のところで地面を固めたい所が出てきました。
今度は土に少量のセメントをませぜて水を撒いて固めるという安易な方法で対応。ちゃんと固まってくれました。
まあ広い面積やると6価クロムなどの問題が起こるそうですが、ちょっとやるのには良い方法です。
【データ】
製作時間;2週間ほど(3時間/日)
費用;消石灰2袋 約1000円