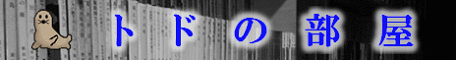琵琶湖東岸の旅
4月11日から二泊三日で琵琶湖東岸を旅して来ました。旅程は以下の通りです。
1日目:広島→石山→MIHO Museum→信楽(陶芸体験)→石山(泊)
2日目:石山→石山寺→三井寺→近江八幡(八幡堀めぐり)→彦根(泊)
3日目:彦根城とその周辺散策→彦根→広島
元々「桜の彦根城」を狙って計画した旅です。
初日の行程は公共交通機関が不便なためレンタカーも検討したのですが、色々経路を工夫して何とか公共交通機関だけで移動できるコースを組みました。
1日目

古代エジプトの隼頭神像
【MIHO Museum】
石山から信楽に向かう山中に桃源郷をイメージして建築された博物館です。ギリシア、ローマ、エジプト、中近東、ガンダーラ、中国、日本など、幅広い地域と時代の古美術品を収蔵しています。バックは某宗教団体ですが、展示そのものには宗教色は有りません。
早朝の5:25に家を出て1時間に1本しかないMIHO Museum行きバスの始発便に乗るべく石山駅に。少し早めに着いたのですが、平日にもかかわらず臨時便が出るほど。その臨時便さえ満員でしたが何とか座れました。外人さんも結構多いので、後で調べてみるとミシュランの三つ星観光地の一つに選ばれたそうです。
バスで50分ほど、到着したレセプションから先の歩道は見事な枝垂桜の並木です。「桜の彦根城」は駄目でしたが、ここで桜を満喫です。並木の先にはトンネルと橋、全部で700mほど歩くと、ほぼ地中に埋まった形で美術館があります。
展示物は見事でした。期待していたギリシア、ローマ、エジプト関係は数こそやや少なめでしたが質的には素晴らしいものでした。中近東や中国のものも見ごたえがありました。
開催中の展示会は「猿楽と面」。最初は興味深く見ていましたが、膨大過ぎて最後はちょっと疲れました。
ここのカフェテリアかレストランで昼食の予定だったのですが長蛇の列です(配膳が遅い感じです。ちなみに自然農法食材で、これがこの美術館で最も宗教色が強く出ているところ)。仕方なくレストランに併設したパン屋さんでドーナッツとメロンパンを買い、外のテーブルで桜を見ながら簡単な昼食にしました。
次は信楽まで、これも1時間に1本しかないバスです。現れたのはマイクロバス、しかも乗ったのは私たち夫婦のみ。タクシーに乗ったみたいにバスの運転手さんと話をしながら20分ほどで信楽に到着しました。


【信楽】

予約した陶芸体験教室まで少し時間があるので、窯元散策路なるものを歩いてみました。
しかし人が居ません。少人数の団体ツアーを2組くらい見ただけ、私たちのようなフリーの観光客は他に見かけませんでした。余りに人が居ないので窯元にも入りづらい。ようやく登り窯を見つけて、それらしくなりました(ちなみにここは休業日でした)。
早めに陶芸体験の店についたら、ここも予約は私たち夫婦だけ。既に準備も整っているとのことで早速開始です。色々なコースがあるのですが、難易度の高い"電動ろくろ"です。
土殺し→成形→口作り→底切りまでが一つの作業ですが(その後、乾燥→高台削り→乾燥→釉薬→焼成)、客がやるのは「成形」と底切りした器を横の台に移動するだけで、あとは付きっきりで説明してくれたお店の人(20代?の女性)がやってくれます。確かにちょっと素人には難しそうです。
成形はこんな手順です。
- 土殺しでセンター出しされた粘土の真ん中に、ろくろを回しながら親指を第一関節くらいまで突き刺して穴をあける。
- 両手の指の腹で挟み込むようにしながら少しずつ筒状に持ち上げて行く(筒形の湯呑になります)
- 茶碗にする場合は、この状態から同じく両指で挟みながら、徐々に手前に倒して口を広げていく(下の写真)
よくテレビで見るようにへなへなと崩れたり(これはもう廃棄)、口の部分に亀裂が入ったり(これは店の人が糸で切り取ってくれるので再成形)しましたが、家内と二人で7つほど湯呑(?)や茶わん(らしきもの;笑)を作りました。一人1つは料金内で、それ以外の焼成は追加料金なのですが、太っ腹な家内は一言「全部焼いてください」。
さてどんなものが出来てきますやら。。


思ったより早く終わって、予定より一本早い電車(こちらも1時間に一本の単線ジーゼル線の信楽高原鉄道)に通学帰りの高校生たちに混じって乗りました。切符は乗り継ぎのJRと共通券なのですが、久しぶりに裏の白い切符を見ました。貴生川駅でJR草津線に(同じホームの向かい側)、さらに草津で東海道本線に乗り換えて石山駅に到着。ここで朝、コインロッカーに入れて置いた荷物を取り出して、駅前のビジネスホテルに宿泊です。


2日目
【石山寺】
再び石山駅のコインロッカーに荷物を入れてバスに乗って7-8分で石山寺へ。朝8時の開門の数分前に到着です。
門が開くと、石畳の道が真っ直ぐに伸び、モミジの若葉が覆っています。竹ぼうきで掃除されてる中、一番乗りの拝観です。
狭い谷間を這い上がる様に作られたお寺です。奇岩、苔むした岩、モミジの若葉、あちこちに咲く山躑躅。早朝のため観光客もまばらな為に、しっとりとした静寂が漂う、とても良い雰囲気のお寺でした。
紫式部の縁で有名で、桜の名所でもあります。桜が見られなかったのは残念ですが、静かにのんびりとこの雰囲気に浸れたのだとしたら却って良かったのかもしれません。








【三井寺】
石山寺から瀬田川沿いに10数分歩いて、今度は京阪電車の石山寺駅から三井寺駅に向かいます。
駅から三井寺に向かって川沿いに歩いて居たら、これが琵琶湖疎水でした。取水口でしょうか、ツアー客が説明を受けています。
三井寺は谷と言うより山の斜面に建てられた大寺です。
広々として砂利道など目立つので石山寺のしっとりした感じには劣りますが、建物が素晴らしい。いずれもすっきりと美しく、とても見ごたえがありました。
この二寺が結構見ごたえがあって結局2時間近く予定オーバー。これも自由な旅の特権です。





回転式の巨大な八角輪蔵

通船でのツアーがあるようです。
【近江八幡】
三井寺から再び京阪電鉄で石山駅に。コインロッカーから荷物を取り出して今度はJRで近江八幡へ。
遅い昼食は駅からほど近いティファニーと言うレストランで、ちょっと贅沢に近江牛ステーキランチ。一口含んで「う~~ん、旨い」。まず広がるのは脂の旨味、噛んでいるうち肉の味が遅れてきます。普段の安いお肉とは全く違います(笑)。観光客向けと言うより地元のちょっと良いレストランという感じのお店でした。
観光の中心は八幡堀です。駅からは少し距離があるのでタクシーで移動。運転手さんがさりげなく観光コースを走ってくれました。
瓦博物館をちらっと見てから八幡堀の周遊船に乗ります。乗り合い式の不定期便ですが、この時の乗客は私たち夫婦のみ、貸し切り状態です。堀を35分ほどかけて往復しますが、風情あるお堀は最初の半分くらいですね。とは言え、よく時代劇にも使われる風景でこれぞ近江八幡です。




すぐ近くの日牟禮八幡宮には14日から行われる八幡まつり(火祭り)のための松明が立ってました。勇壮な祭りの様ですね。
八幡宮の向かいにはバームクーヘンで有名なクラブ・ハリエがあります。ここでケーキとコーヒーで一服してから、近江商人の古い町並みが残る新町通りへ。見事な街並みですが意外に短い。内部公開している所もある様ですが、全く気付きませんでした。これなら広島の竹原の方が立派だね(豪商家屋の大広間は見ごたえがあります)と言いながら、ここらでもう足も限界です。


近くの停留所からバスに乗って近江八幡駅、JRで彦根駅に着いて駅裏のビジネスホテルに宿泊。ホテルから見た彦根城の夕日が綺麗でした。
ちなみに夕食は軽く駅前で「近江ちゃんぽん」でした。小さな店でしたが、現在全国展開しつつあるチェーンの発祥の店だったのですね。ちなみにうちの近くのショッピングモールにも出店してます。でもやはり本店の方が美味しい気がします。

3日目
【彦根城】
例によって開門時間狙いでホテルを出ます。
表門の料金所を抜けるといきなり急坂です。途中、天平櫓の内部公開を見て本丸へ向かいます。いわゆる桝形(城郭の入口に作られた石垣で囲まれた方形の空間。敵を呼び込み上部から攻撃する)は小ぢんまりしていて、珍しい堀切とそれを超える橋があります。傾斜面に作られた登り石垣とともに、山城らしい作りです。


街から見上げると下半分が木々に隠されているため、もっと多階層の建物に見えるのですが、実際には三層の小さな天守閣です。
中は予想以上に明るかったですね。と言っても他に唯一行ったことがある現存天守閣の姫路城が暗かった印象が強いだけですが。
朝早いので人も少なくゆっくり見ることができます。急な階段(というよりハシゴ。スカートでは行けませんね)を登って最上階。琵琶湖が綺麗です。



10:30には本丸前広場にひこにゃんが登場するようですが、無視して(笑)裏手の西の丸三重櫓(登ると琵琶湖からの風が強烈でした)を経て楽々園/玄宮園へ。このあたり来るとほとんど人が居ません。モミジの若葉の小道、貸し切り状態です。


楽々園(彦根藩の二の丸御殿の建物部分)の建物がすっきりして良い感じです。玄宮園(同、庭園部分)は大きな池を中心にした回遊式庭園です。広島の縮景園(浅野家の庭)が滝や築山を細かく造成し、東屋を点在させているのに比べ、後ろに彦根城を控えざっくりとした大らかな作りです。のんびり散策したのち、一カ所にまとまった数寄屋建築の八景亭で抹茶を頂きます。前はお庭、後ろはお城、大名気分です。
そのままくるりと彦根城の表門に廻って、今度は彦根城博物館へ。井伊直弼さんて安政の大獄とか強権なイメージがあるのですが、居合とか茶の湯とかずいぶん多才な人だったのですね。復元された表御殿のもなかなか見ものでした。




【キャッスルロード】
お昼を頂こうとキャッスルロードへ。
江戸時代の城下町をイメージして白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みです。ちょっと新し過ぎて、無理している感じもあり、風情というほどのものは有りませんが。
ほとんどは飲食店とお土産物屋さんなどですが、たまに銀行やら新聞社もあって、それらも全て白壁黒格子。力が入ってますね。銀行(関西アーバン銀行)が「両替商」の看板を挙げているのが家内に受けていました。
軽い食事をして、お土産物(先ほど抹茶と一緒にいただいた彦根銘菓;埋もれ木が美味しかったので)を買って、少し早めなのですが帰路につきました。
まとめ
信楽でパラリと降られましたが、全体的には良い天気に恵まれました。そして、その中を良く歩きました。三日間で55000歩、最後は足に来て、それ以上歩き回る気力がなくなるほどでした。
元々は桜狙いだったのですが。。。
でも桜を外したぶん、人が少なくのんびり旅ができたような気がして、それはそれで良かったのかと。