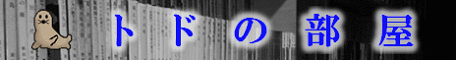弁才船河市丸の復元模型6
船室の屋根
船室の屋根は大きく三分割されてます。
中央、歩(あゆむ)と呼ばれる二本の太い棟の間は帆柱を倒すためのスペースですから、天井板も取り外し可能。碁板と呼ばれる四角い板が一列に並んで敷かれます。その左右は普通に固定式の屋根なのですが、そうするとせっかく作った船室内部が二度と見え無くなってしまいます。
受け木(桟)と天井板(雨漏り防止のため1㎜の2枚合わせ)は接着し、根太には桟を乗せる溝を掘るが接着はしない。これで天井は外れますが桟が付いていても薄っぺらい板状なので強度的に不安です。そこで桟を3㎜角の鋼棒(ネットで購入)にし、天井の下側の板と鋼材は透明な釣り糸で絡めながら接着し、その上からもう一枚板を貼り付けました。これで表から釣り糸は見えず、強度的にもOKです。
平行しながら垣立も細かな仕上げをしていました。
扇形の銅板はレザークラフト用の直径8㎜と2㎜のポンチとを使ってドーナッツ状に抜き、それを120°で3分割したもの。一個一個見ると個性的(笑)なのですが、並べると綺麗でしょ。
垣立全体の固定は梁の下から細い木ねじで固定しました。本物とは異なりますが、ここは強度優先です。伝馬口と開の口の部品も合わせて接着し、クランプで暫く固定です。


伝馬口 五尺
きっちり固定出来た後で、伝馬口の扉(内・外)を作ります。これらは上に引き抜いて外すようになっています。
そして五尺。船首部の防波板です。
航海中は立っているのですが、停船すると碇を下すために取り払います。大きな一枚板だと思っていたのですが、作る直前になって薄板とその板を差し込む溝を掘った角棒を交互に4段積み上げた構造なのだと気付きました。なるほど、一枚板じゃ人力で扱うのはちょっと重すぎる。
下の2段は船首の頬面(ほほべら)というひし形の板と後ろの五尺立という柱に切った溝で位置が決まる。それより上には頬面が無いので、五尺立と五尺の丑という脱着式の梁で左右を決める。ようやく構造に納得です。
悩んだ末、ここもその通りに再現することにしました。
五尺立周り、一見たいしたことはなさそうですが、これが結構難しい。
内だけでなく前にも傾いたカラカイ立、その上に乗り中央ではの表車立にも接する梁の横山、さらに横山の前に立ち垣立の雨押(手すり)と繋がる五尺立。やたらとつながりが多い上にどれも傾いているのです。
五尺立と水押につけた頬面(ほおべら)に合わせて五尺の板と棒を積み上げて行きます。
でもちゃんとできましたね。ただ、部品がバラバラですから五尺を外したり組んだりは面倒です。


帆船模型には何段階かの完成状態があります。
1)安全祈願に神社等に奉納する模型;
船大工が作ります。舵や碇などの船道具はなく、帆柱も倒して格納した状態です。
・・・古い和船模型の多くはこの形式です
2)帆が無い状態;索具や碇、舵などは装着状態。
ダランと下がった帆は見栄えも悪く、作り込んだ細部を隠すなど却って邪魔なことも多いので帆はつけない。
・・・多くの西洋帆船模型がこの状態です。
3)帆も全て付けた状態;
・・・見映えは良いですが、模型というより装飾品というイメージが強くなります。
ここまでで、当初の目的だった1)が完成しました。
続いて2)3)にも進んでみます。特に3)はやってダメなら元に戻せばいいやという考えです。