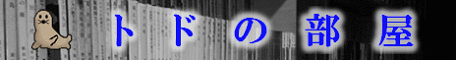
日曜大工が趣味だった父親の道具を引き継いで。。。
何かを作る為の工夫を考えたり、実際に手を動かしていると
機嫌が良いのです。退職後、ますます加速中。
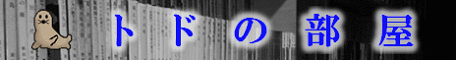
日曜大工が趣味だった父親の道具を引き継いで。。。
何かを作る為の工夫を考えたり、実際に手を動かしていると
機嫌が良いのです。退職後、ますます加速中。
暖かくなって来たので久しぶりのDIY。郵便受けです。
これまで使ってきた郵便受けは2002年に自作したもの。⇒こちら
何せ(ニセモノですが)白壁にベンガラ塗の板壁に似合う郵便受けなど売っていないのです。
とは言え作ってから早18年、板は乾燥しずぎてワレが目立ち、元々設計不良だった横の取出し口も、磁石のキャッチがしばしば外れてだらしなく。
先日はヒンジの木ねじが抜けてしまいました。締め直したものの、もう木が弱り切っている感じです。


で、作り直しです。
雰囲気は変更せず、幾つか改善します。
1) はがきや封書は配達の人が上の蓋を開けなくても投入できるようにする
2) 取り出しやすくする ~奥に入ったハガキ等を取る時、間口が狭くて板の切断部に手が触れて少し痛いのです。
で、出来上がったものはこんな感じ。
ガッパリと前に開いて、なかなか良い感じです。



木目が良いでしょう。
表側とベースの板は「もち板」を転用しました。
この地方の餅は丸餅。丸めた餅が冷めて固まるまで置いておくための板が「もち板」で、幅30㎝、長さ200㎝ほどあります。今でも3枚は現役で毎年暮れに活躍しますが、屋根裏には10枚近く予備が有ります。
これだけの幅の一枚板はなかなか手に入りません。あっても高いですし、分厚すぎます。もっともこの餅板は薄過ぎて(6㎜くらい)弱く、しかも結構ひわっています。そこでまず板を2枚背中合わせに重ねて接着剤で貼り合わせます。
木目を生かすために表面をバーナーであぶって黒く焼き、柔らかな真鍮ブラシをかけると木目が綺麗に出てきます。最後に無色透明の木材保護塗料を塗って出来上がり。いまはやや紫がかっていますが、暫くすると色も落ち着いてきます。


構造的にはこんな感じ。
上蓋の先端に出っ張りをつけ(写真の赤い矢印)前側の筐体が開くのを止めています。筐体を開くときは上蓋をちょっと持ちあげて手前に引くイメージ。但し閉じる時は上蓋を持ちあげなくても大丈夫です。
上蓋を持ちあげただけで筐体がパカッと開くと配達の人が驚くでしょうから、左上部に小さな扉用のキャッチをつけました。片側だけでなかなか良い節度が出ています
開いた時の角度はワイヤーハンガーから採った黒い皮膜付きの針金とトラス頭の木ねじで作ったストッパーで(左右)。
板の大部分は家にあった「もち板」。さらに筐体のヒンジやキャッチなども父親が買い置いていたものなのでタダ。
接着剤や塗料なども残り物。
買ったのは
筐体側面の板=700円
蓋の板=400円
蓋のヒンジ=400円
しめて1500円ほどで出来ました。