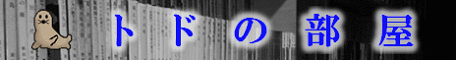建物表題変更登記の自力申請
- 背景
- 自分で登記するぞ~
- 法務局への相談準備
- 法務局との打ち合わせ
- 申請書提出
- バックアップ書類の準備
- 実地検査~登記完了
- 市役所のフォロー
背景
2024年4月から相続登記が義務化されました。過去に相続した分も対象という事で、祖父名義のままの私が住む家も対象となります。回避策も有るのでしょうが、ここはスッキリしておいた方が良いと、2024年の初めから相続協議に着手しました。(ちなみに土地については相続登記は完了しており問題無く、対象は建物だけです)
その過程で私が2000年に改築した部分(水周り)が未登記であることが判りました。市役所はちゃんと完成時にチェックに来て固定資産税も払っています。しかし、登記はされてないのです。
ちなみに市役所で聞いたところ、
・法務局に登記をするとその情報は市役所の課税課に流れる。
・課税課の情報は法務局には流れていない
実はこの家、2度の大改築が行われていて、整理すると以下の状況です
1)祖父が大正時代に母屋と別棟(台所部分)を新築した。
2)1966年頃に父親が改築。母屋を一部減築し、水周り部分を増築。多分この時に別棟も潰した。
3)2000年に私が父親が増築した部分をすべて取り壊し、全面改築。母屋部分も改修したが、柱などは動かしていない。
で、今登記されているのは1)の状態なのです。
自分で登記するぞ~
2024年の初めに相続登記をスタートしました。何せ3世代18人が対象で、うち1人はアメリカ在住という複雑な相続協議のため、司法書士さんに入って貰い進めました。幸い皆さん協力的で5月末にはトラブルなしに完了。ここで登記内容は1)の状態のまま、所有者が祖父から私に変わりました(所有権移転登記)。
次は登記の表題部を3)の最新状態にする建物表題変更登記です。普通は土地建物調査士や司法書士にお願いする様ですが、ネットを調べてみると個人でも出来そうなことが判ってきました。
法務局に提出する書類は
a)申請書
b)所有権証明情報
c)建物図面・各階平面図
の3点です。この内b)の所有権証明情報は建築会社から貰う資料なので、自分で準備するのはa)の申請書(A4一枚)とc)の図面(B4一枚)のみ。個人申請のネックはc)の図面のようですが、私は元設計者(建築ではなく機械製図ですが)なので何とかなるだろうと・・・。
法務局への相談準備
土地建物調査士や司法書士と言ったプロならば申請書を一発出せば終わりなのでしょうが(実際ネット上でも申請できる)、素人はそうもいかず、調べてみると法務局に予約制の相談窓口があります。
とは言え、徒手空拳で行く気にもならず、出来る書類は作っておいて相談に向かう事にしました。
a)申請書→詳細はこちら
ネットでサンプルを見つけ、それをもとに作成。
b)所有権証明情報→詳細はこちら
ここが一番相談したいところ。
増改築などの場合、工事完了引渡証明書などがそれにあたるようですが、一切ありません。そこでネット上にあった固定資産税台帳登録事項証明書と上申書のサンプルを持って相談に臨むことにしました。
c)建物図面・各階平面図→詳細はこちら
これも当時の図面は残っていません
市役所で閲覧した固定資産税評価用の間取り図を基に図面を作成しました。
ちなみに父親の改築については、全て潰して残ってないので一切触れないという方針です。うっかり触れると法務局でも無視できなくなったりして、ただでさえ複雑なのが余計ややこしくなるだけなので。
法務局との打ち合わせ
予約して受付に行き、そこで受付用紙に氏名など記入して相談窓口に行くと、再就職シニアっぽいオジサンが、背もたれに体を預け、腕を組んで目をつむって(笑)
準備した書類一式を見せると、簡単な書式チェックと各階平面図の面積計算をチェック。
所有権証明情報が無い事を伝えると、事務所内に向かい、何か相談しています。その後となりの窓口に行けとの指示。ここで先ほどオジサンが相談していた女性が出て来ました。どうもこの人が本丸らしい。
その女性から指摘されたのは、
a) 申請書
基本スタンスに差があります。私は既に決定済みの市役所の固定資産税台帳に合わせたい。法務局は「市役所なんて知らん」という姿勢。具体的に言うと私は固定資産税上は古い母屋部分と改築部は別扱いのため、この二つを区分できるように作っていたのですが、法務局としてはそんな区分無しに最新の全体像だけを書くようにという指示です。
b) 所有権証明情報
増築部の所有権については固定資産税台帳登録事項証明書と上申書でOKとの事。また、申請書に書いていた旧家屋を一部取り壊し、増築したといった経緯を書くなら上申書に書く方が良いとの指導がありました。
ところが思いもよらぬことに母屋部分の所有権についても言及があり、遺産分割協議書類一式(分割協議書+戸籍謄本+印鑑証明)を提出するようにと云われました。そもそも5月に所有権移転を法務局で完了しており、色々な理由で一部の戸籍謄本や印鑑証明は本人に返却しているので「提出は無理です」と言ったら納得してくれました。
c)建物図面・各階平面図
描き方について色々指導がありました。
いずれも、設計者としてはごく常識的な表現なのですが、どうも一般製図ルールは通らないようです。
申請書提出
上記指摘に合わせて、全ての書類を修正しました。上申書には実印を押すので、印鑑証明も入手(マイナンバーカードがあればコンビニで取れるので楽です)
再度予約して受付で受付用紙を記入して相談窓口に行きます。
相談窓口のオジサン、例の姿勢で待機中(笑)
書類を出したら、内容をざーっと目を通して「OKです。受付用紙を持って受付に戻って」と言われて戻ると、受付用紙に何やら追記したうえで「今度、現地調査に行きますから」と連絡電話番号を確認され、全部で10分ほどで解放。どうやらこれで申請受付は終わったようです。エエ?こんなもの?
どうも窓口のオジサンの役割は書式チェッカーらしい(中身はタッチしない)。
その後、担当になったという女性から図面の修正指示の電話が2度ありました。内容は詳細ページを見てください。
バックアップの準備
実は・・・・
図面を提出した時に気付いたのですが、トイレの出っ張りが図面(市役所)と現物で倍半部(33㎝ vs 73㎝)違います。理由は分かりませんが、これを現地調査で指摘されると・・・
そこで、実測ベースで書き直した図面と、それに合わせた申請書、上申書を現地調査前に準備しました。
(建物面積で言えば小数点以下の差しかないのですが・・)
現地調査~登記完了
数日前に電話があって、女性が三人来られました。(申請書提出の2週間後)
トップは電話してきた人、子分1が相談した人、子分2はどうも一番下っ端の様です。
家の全周をメジャーで測定していきます。そして予想通りトイレの出っ張りが問題指摘されました。
一旦家に上がってもらい、経緯(市役所の図面をベースにしたのでこうなった事。提出後に気付き、新たな図面を準備している事)を説明。図面と上申書をその場で再提出しました。申請書については法務局で修正するとの事で現地調査は完了しました。申請書も準備はしていたのですが受付済みの申請書の差し替えは出来ないようです。
そして・・・ なんとその日の夕刻、審査完了の電話連絡があり、翌朝、法務局に出向き「登記完了証」なるものを頂き、全ての登記作業が完了しました。
=========================
図面のP/O(B4のプリンターが無いため、コンビニで出力)、市役所で幾つかの書類の入手(1件300円ほど)は有りましたが、全部で2000円も掛かりませんでした。本職にお願いすると80000円ほど必要なようです。
市役所のフォロー
登記情報は法務局から市役所に流れて行きます。
2000年から何も変わっていないので市役所における固定資産税上の変更は無いはずですが、面積が若干変わっていたりします。市役所を混乱させてもしょうがないので、登記完了の数日後に近くに行った際に市役所の課税課に立ち寄り、登記の経緯を説明しておきました。
・未登記建物(増築部)の登記を行ったので、法務局から情報が流れてくる事
・市役所の図面で登記しようとしたが、実物との差があり修正したこと
・実際には、市役所が把握している2000年増改築から何も変化はない事
いらぬおせっかいかな~